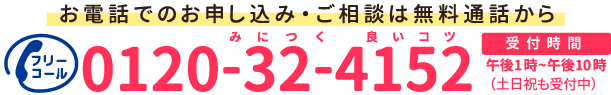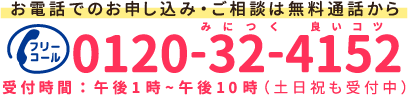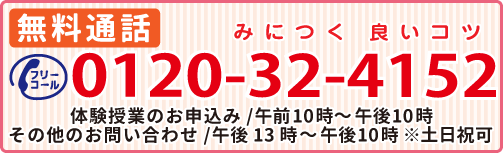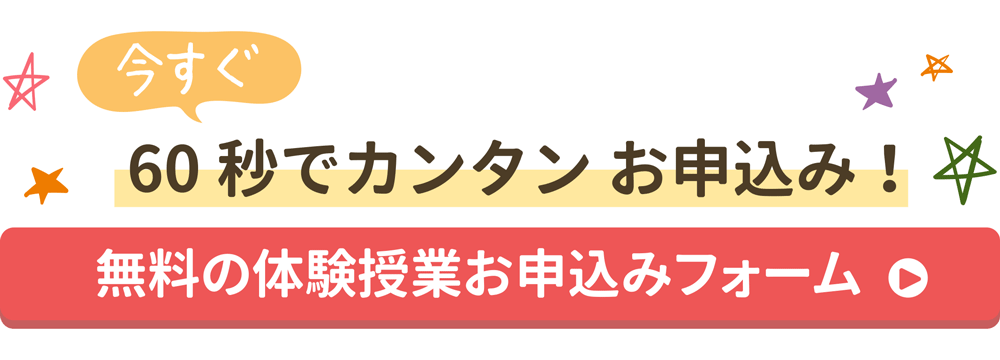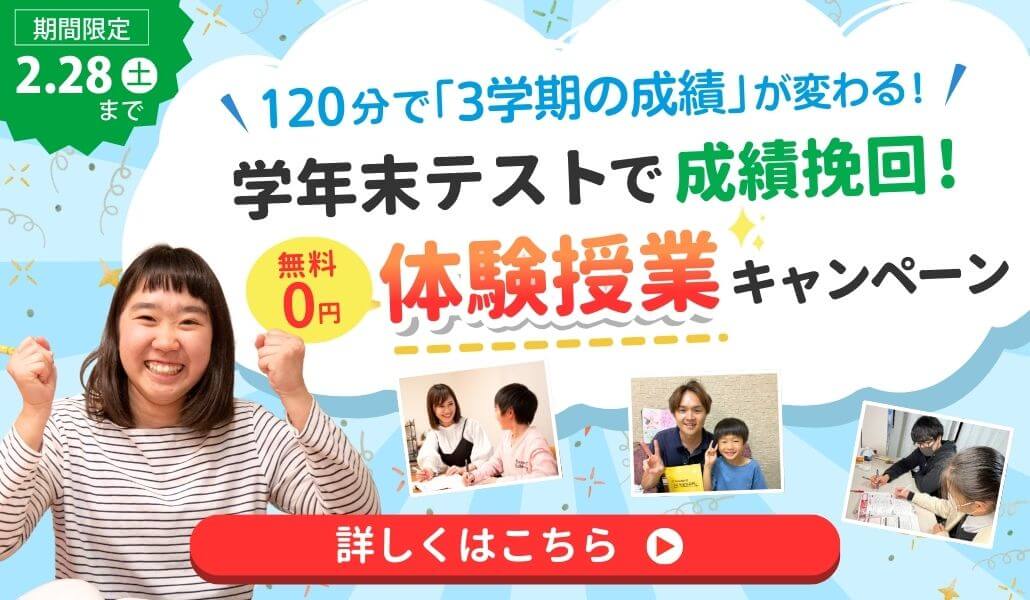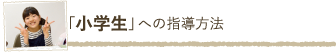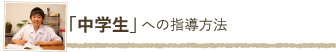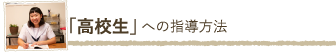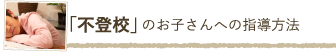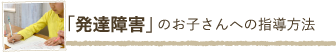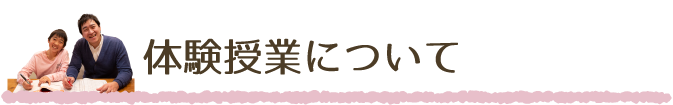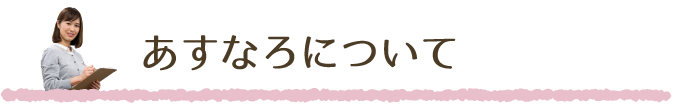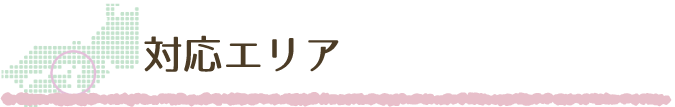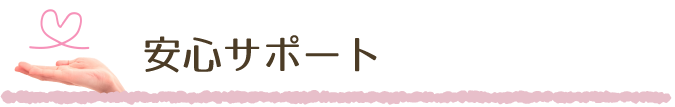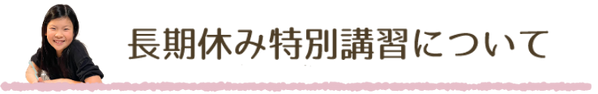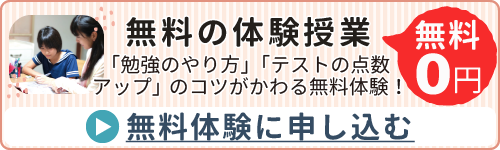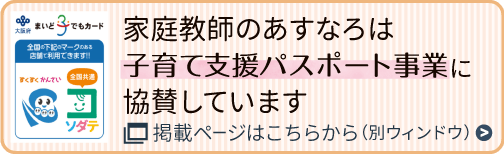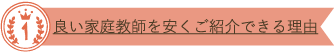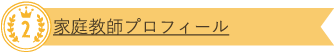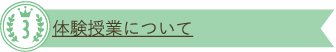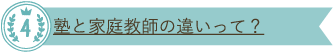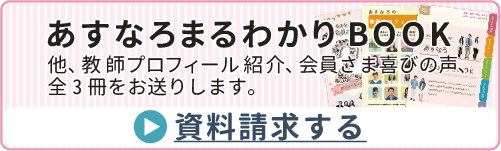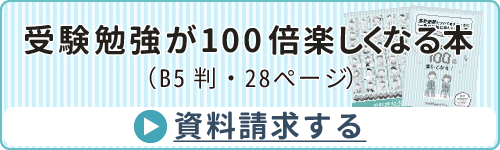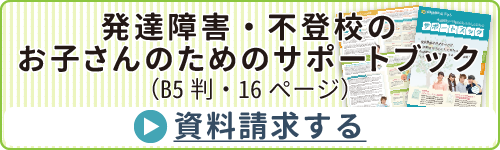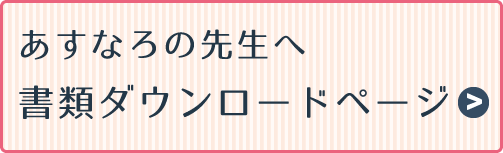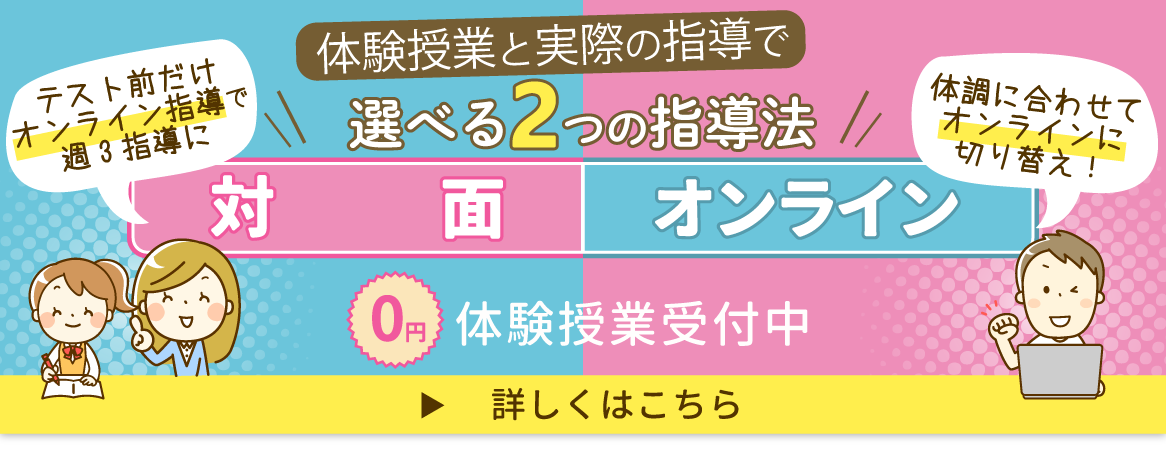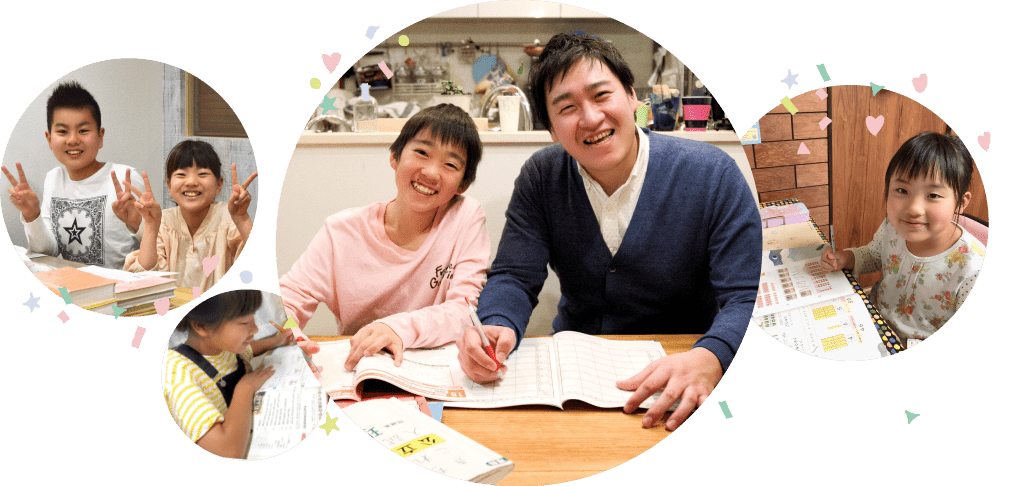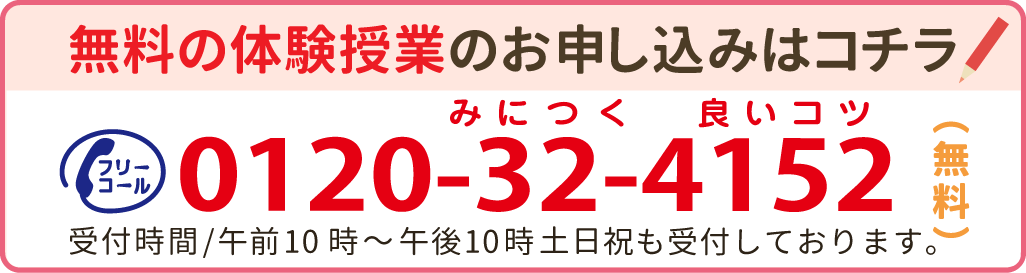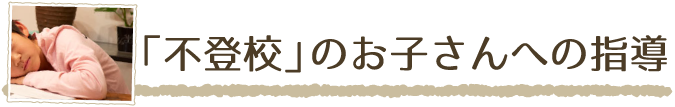小学生の頃は、特に勉強を意識しなくてもテストで良い点を取れていたという人も多いと思いますが、中学生になると勉強が難しく感じたり、部活動で勉強時間が取れないという悩みを抱える生徒が増えてきます。
中学校の定期テストでは、小学校のテストとは異なり、テスト前の準備が成績に大きな影響を与えます。
では、中学生になってからのテスト勉強はどのように進めるのが最適なのでしょうか?
この記事では、定期テストに向けた効果的な勉強法やスケジュールの立て方、勉強を始める時期、そして勉強において重要なポイントを詳しく解説します。
=もくじ=
中学生の定期テスト対策はいつから始める?
中学生にもなると、定期テスト前にはテスト勉強が欠かせなくなります。直前で慌てないよう、早めに勉強を始めましょう。
ただ、あまりスタートが早すぎてもやる気が続きません。そのため、中学生の定期テスト対策は以下のタイミングで始めるのがお勧めです。
期末テストの場合
期末テストでは中間テストよりも教科数が増えるため、より早めにテスト勉強を始めなくては間に合いません。
実技系の教科ももれなく勉強するためには、テスト3週間前から対策を始めるのがおすすめです。
中学生のテスト勉強時間は1日どれくらい?
中学生の定期テスト対策では、1日に何時間勉強すればいいのでしょうか。
無理なく部活動と両立するためにも、以下のように、時期により勉強時間を変えることをお勧めします。
定期テスト1週間前まで
部活動があると、平日にまとまった勉強時間を確保するのは難しいものです。無理なく勉強できる時間を見つけることが大切です。夜寝る前や朝の登校前などの隙間時間を活用して、1日1時間は勉強することを目指しましょう。
定期テスト1週間前からテスト前日まで
テストの1週間前から部活動が休止になるので、この期間は平日1日3時間を勉強に充てるようにしましょう。朝1時間、夜2時間など、時間を分けて勉強しても問題ありません。
また、学校が休みになる土日には、できる限りテスト勉強に集中してください。理想的には1日8時間以上の勉強を目指しましょう。
中学生の定期テストの効率的な勉強法とは?
テスト勉強=暗記と思われがちですが、そればかりではありません。限られた時間の中で効率よく勉強するためにも、教科に合った勉強法を実践する必要があります。
暗記型教科と積み上げ型教科
教科は「暗記型」と「積み上げ型」に分けられます。
暗記型教科は、主に暗記によってテストに対応できる教科です。各単元が独立しており、過去に学んだことを忘れても、今回のテスト範囲さえ覚えていれば点数を取ることができます。
積み上げ型教科は、基礎をしっかり学んでいくことで、次に学ぶ内容が理解できる教科です。前に学んだ内容が定着していないと、次の単元で困ることになります。
中学校の社会は暗記型教科に当たります。国語と理科も、どちらかと言うと暗記型に分類される教科です。
反対に、英語と数学は積み上げ型教科です。各単元をしっかり理解し、着実に学びを積み重ねていくことが求められます。
主要5教科の勉強方法
以上を踏まえ、中学生の定期テストの勉強法を、主要5教科別にご紹介します。
どの教科も1日2日では対策しきれないため、テスト勉強は余裕をもってスタートしましょう。
英語
英語の基礎となるのは、文法と単語です。試験範囲に出る文法と単語は、確実に覚えましょう。単語の暗記には書くだけでなく、声に出して読むことも効果的です。
さらに、教科書の英文を和訳することに取り組むと、覚えた内容が記憶に残りやすくなります。試験範囲にある長文は、音読と和訳を一通り行いましょう。
数学
数学では、まず公式を覚えることが基本です。しかし、覚えた公式を使いこなすためには、問題に公式を適用し、応用力を養う練習が必要です。
そのため、問題集などを使って多くの問題に取り組むことが、数学を効果的に学ぶ方法です。分からない問題があれば、そのままにせず、すぐに先生に質問して解決しましょう。
国語
漢字や文法、古語は暗記することで確実に点が取れる得点源です。繰り返し覚えて、確実に正解できるようにしましょう。
一方で、得意・不得意が分かれる読解問題では、どの部分に注目すべきかが重要です。教科書やノートを見返して、注意すべきポイントを復習し、その後は演習問題を解いてコツを掴みましょう。
理科
理科では、語句の暗記が必要です。時間をかけて少しずつ覚え、その後は定期的に復習して忘れないようにすることが大切です。
さらに、公式や法則をしっかり理解するために、暗記と並行して演習問題にも取り組むようにしましょう。
社会
社会は暗記が中心の科目ですが、語句を個別に覚えると混乱してしまうことがあります。各語句の関連性やつながり、出来事の流れを理解し、関連する言葉を整理しておくことが大切です。
そのためには、単に暗記するだけでなく、教科書をしっかり読み込み、理解を深めることが必要です。教科書の内容を自分の言葉でノートにまとめると、より記憶に残りやすくなります.
副教科の勉強法
期末テストでは、主要5科目に加えて副書の筆記試験も実施されます。
中学生の副教科書のテストは、担当の先生によって出題内容が異なります。つまり、先生の授業ノートや配布されたプリントが最も重要な参考資料になります。
副教科書は主に暗記が求められます。授業内容をしっかり復習すれば必ず量につながりますので、後回しにせず早めにじっくり考えましょう。
定期テストに効果的な勉強計画・スケジュールの立て方は?
限られた時間内で確実にテスト勉強をこなすには、事前の計画が欠かせません。
続いては、テスト勉強のスケジュールの立て方を説明します。
試験範囲と必要な勉強量を把握する
テスト範囲が発表されたら、まずはその内容を詳しく確認しましょう。ページ数や問題数、暗記すべき単語の数などを具体的に把握することで、どれくらい勉強すればよいかが分かります。
1日に勉強する量を決める
全体の勉強量が把握できたら、1日ごとの勉強量を設定します。この時、単純にページ数を日ごとに分けるだけでは、問題数や暗記すべき単語数が日によって偏ってしまいます。内容や難易度を考慮し、無理なく取り組める量に分けることが大切です。
計画表を作成する
毎日の勉強計画を作成したら、そのスケジュールを表にまとめましょう。視覚的に確認できるようにすることで、計画と実際の進捗にズレが生じた場合に、現状を把握しやすくなります。さらに、その日に実際に勉強した量や内容を記入するスペースがあれば、さらに便利です。
変更のたびに計画表を修正する
時には計画通りに勉強が進まないこともあるかもしれません。その場合は、計画を見直し、スケジュールを修正しましょう。ズレをそのまま放置しておくと、テスト直前に取りこぼしや計画の崩れが発生する可能性があります。3日に一度は修正を行うことが重要です。
定期テストの勉強で大切なこと
このほかにもテスト勉強に取組むうえで心がけておくべきポイントがあります。
最後に中学生の定期テストの勉強で大切なことを4つ、ご紹介します。
わからないところはすぐに質問する
疑問点を後回しにすると、後々困る原因となります。テスト勉強中にわからない問題に出会ったら、翌日には先生に質問しましょう。毎日学校に通っているので、先生に質問できる機会を積極的に活用するべきです。
まとめてやろうとしない
人は覚えたことを忘れてしまいます。テスト1週間前に英単語を一気に覚えても、その後全く復習しなければ、テスト当日までに多くを忘れてしまうでしょう。テスト勉強は一度にまとめてやろうとせず、普段から計画的に取り組み、繰り返し復習することが大切です。こうすることで、記憶がしっかり定着します。
徹夜は効率が悪い
人の記憶は睡眠中に整理され、脳に定着します。徹夜で無理に覚えた内容は、長期的には記憶として残りにくくなります。さらに、眠気と戦いながら勉強することはストレスを溜め、効率も落ちます。従って、徹夜での勉強は避けるべきです。効果的なテスト勉強には、十分な睡眠が不可欠なのです。
テストで間違えたところは復習を
定期テストが終わり、勉強から解放された喜びで、返却された答案をそのまま放置していませんか?特に積み上げ型の教科では、各単元をしっかり理解していないと、後の単元でつまずく原因になります。テスト後には間違えた部分を復習しておくことが、次のテストでの得点アップに繋がります。
まとめ
中学生の定期テストでは、各教科に適した方法で計画的に勉強を進めることが重要です。テスト範囲が発表されたら、すぐに勉強スケジュールを作成しましょう。
中学生の場合、中間テストの2週間前、期末テストの3週間前から勉強を始めるのがベストです。部活がある日でも最低1時間は勉強するようにしましょう。部活が休みの平日なら、1日3時間の勉強が理想的です。
徹夜や短期間での詰め込み勉強は効果が薄く、地道に反復学習を続ける方が効率的です。わからないところは先生に質問し、テスト後の復習も忘れずに行いましょう。