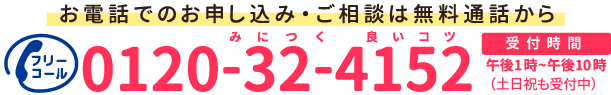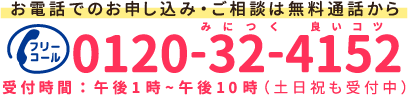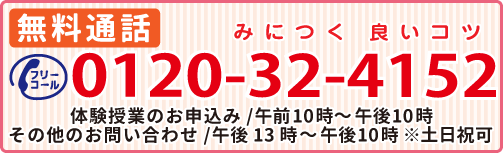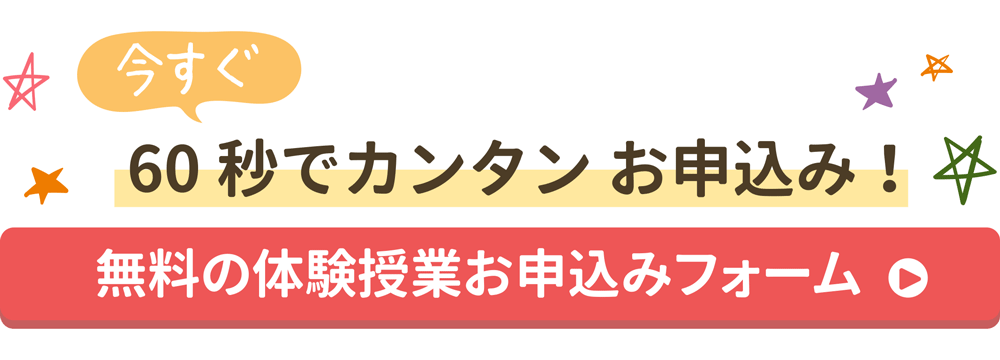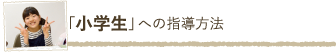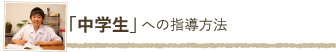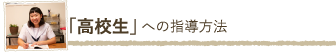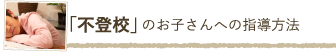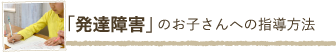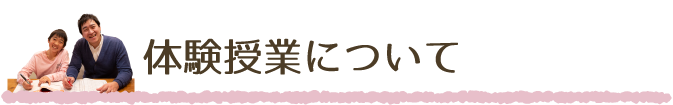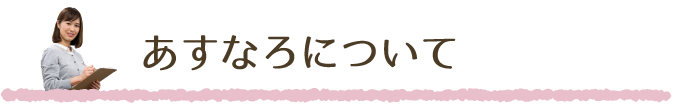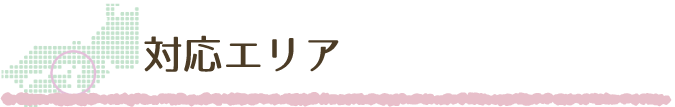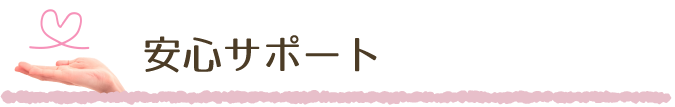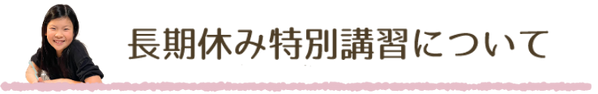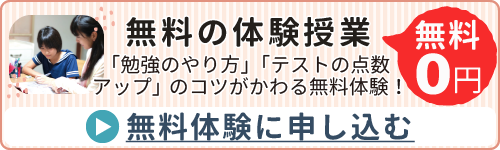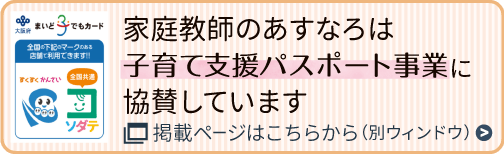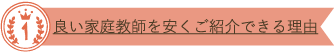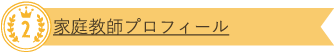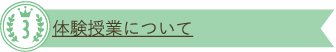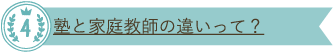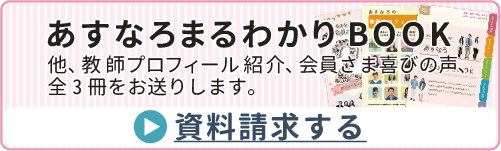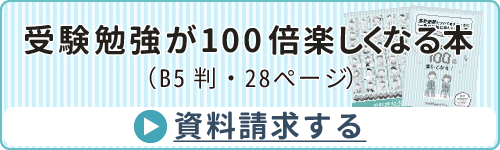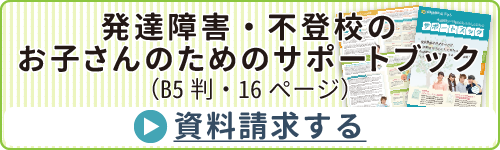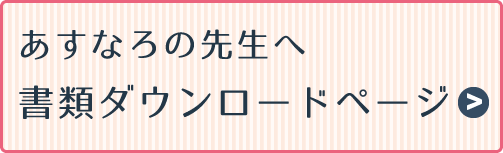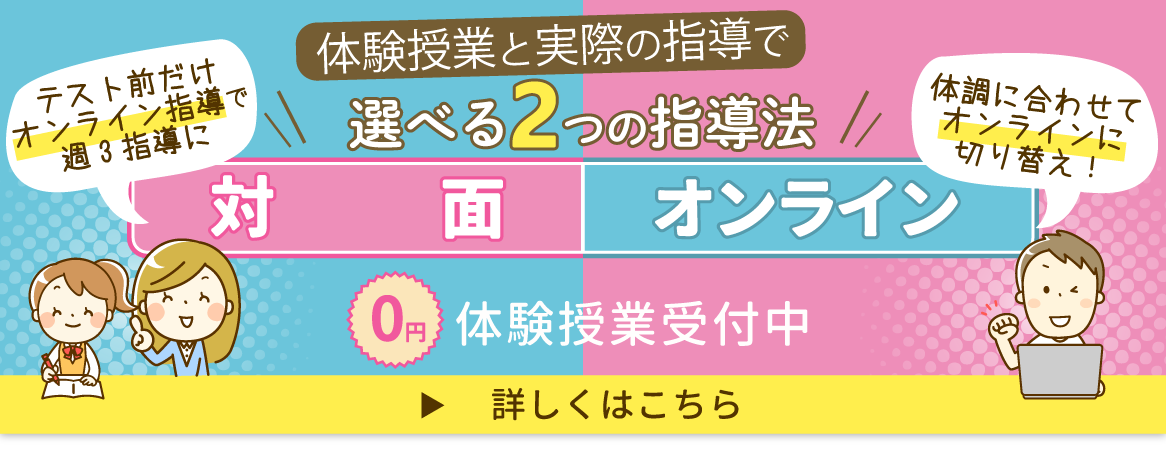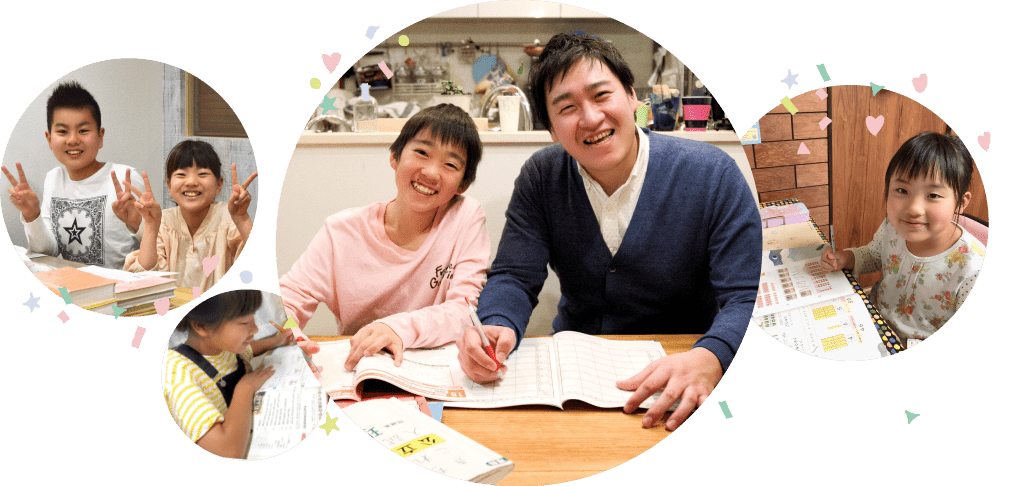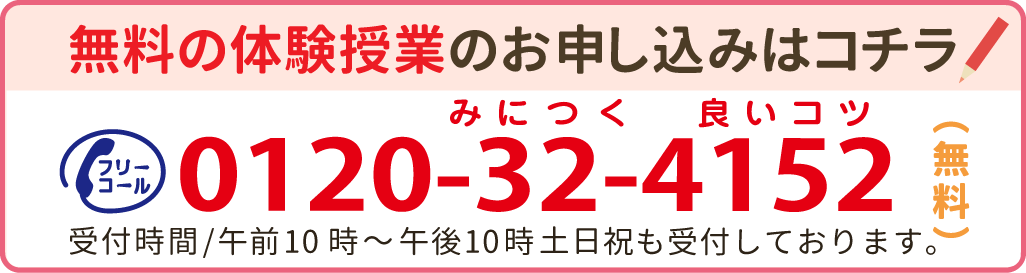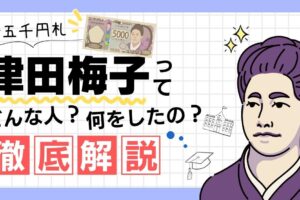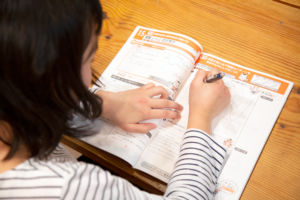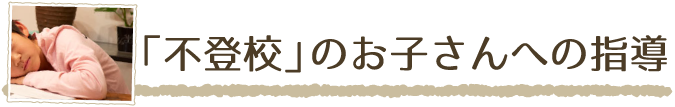4月が終わり、お子さんも保護者さまも新たな学校生活に少しずつ慣れてきたのではないでしょうか?
近年、教育現場や子育ての場面で「非認知能力」が重要視されています。学力テストなどで測られる「認知能力」とは別に、お子さまがこれからの社会で自分らしく、たくましく生きていくための土台となる力として注目されていますが、なぜ今、この非認知能力が重要視されているのでしょうか。
そこで今回は、お子さんの未来の可能性を広げる鍵とも言われる「非認知能力」が、具体的にどのような力を指し、どのように育んでいけば良いのかについて、詳しく解説していきます。
=もくじ=
「認知能力」と「非認知能力」とは?
まずは、基本となる「認知能力」と「非認知能力」について整理しておきましょう。
認知能力は点数で測定可能な能力
認知能力には、IQ(知能指数)や学力テストの点数などで測定可能な、知識の記憶、計算力、読解力、論理的思考力などが含まれます。学校教育で重点的に育成される部分であり、知識や情報を効率的に処理し、問題解決につなげるための基盤となる力です。
非認知能力は個人の内面的な力
非認知能力は数値化することが難しい、個人の内面的な能力を指します。具体的には、以下のような多様な要素が含まれます。
| 目標達成に 関する力 | 他者との関わりに 関する力 | 感情のコントロールに 関する力 | 知的好奇心や 創造性 |
| 意欲 粘り強さ 忍耐力 自制心 計画性 | 共感性 協調性 社交性 リーダーシップ 思いやり | 自信 楽観性 回復力(レジリエンス) 自己肯定感 | 新しいことへの関心 探求心 想像力 |
これらは、テストの点数には直接現れにくいですが、人生のあらゆる場面で必要とされる「生きる力」の核となる部分だと言われています。生まれ持った性格だけに依存するものではなく、経験や環境を通して後天的に伸ばしていくことが可能なスキルです。
なぜ今、「非認知能力」が求められるのか?
変動が激しく、先が見えにくい今の時代、ただ知識を蓄えるだけでは足りません。人工機能の技術も高まっているため、これからの人材に求められるのは、人工知能に真似できない人間ならではの力です。そして、その人間ならではの力とは、周りと協力する力、新しいことを生み出す力、困難に立ち向かう粘り強さ、自分の気持ちを調整する力といった、数値として評価できない「非認知能力」のことです。
研究によって、この非認知能力は、将来の学業、仕事、収入、健康にも良い影響を与えることがわかっています。つまり非認知能力は、単なる学力のためだけでなく、お子さんが将来社会で活躍し、幸せに生きていくために、非常に大切な力なのです。
お子さんが非認知能力を鍛えるメリット
お子さんの非認知能力を育むことには、具体的に以下のような多くのメリットが期待できます。
勉強にいい影響を与える
目標設定能力、計画性、自制心、粘り強さなどの能力が高まることで学習習慣が身につき、難しい課題にも諦めずに取り組む姿勢が育ちます。結果として、認知能力(学力)の向上にも繋がるでしょう。
人間関係をより良いものにする
共感性や協調性が育まれることで、友人や家族、社会との円滑なコミュニケーションが可能になり、互いを尊重し合える豊かな人間関係を築くことができます。
メンタルの安定と成長
自己肯定感や回復力(レジリエンス)が高まると、失敗や挫折を乗り越え、ストレスにうまく対処できるようになります。変化の激しい社会においても、精神的な安定を保ち、前向きに挑戦し続けることができます。
主体性が育つ
自らの興味関心に基づいて目標を設定し、意欲的に挑戦し続ける力は、受け身ではなく、自ら人生を切り拓いていくための原動力となります。
非認知能力はどうやって鍛える?
では、非認知能力はどのように育んでいけば良いのでしょうか。以下に具体的なヒントをいくつか紹介します。
結果ではなく、結果に辿り着くまでの過程を評価する
テストで100点を取ったという結果だけでなく、「難しい問題に粘り強く取り組んだね」「計画的に勉強を進められたね」といった努力の過程や工夫を具体的に認め、褒めることで、お子さんの粘り強さや計画性が育まれます。
失敗しても責めない
お子さんが何かに挑戦した時、たとえ失敗しても責めるのではなく、「次はどうすればうまくいくか」を一緒に考える姿勢が大切です。失敗は学びの機会であると捉えることで、回復力や挑戦する意欲が育ちます。
お子さんの疑問や感情を大切にする
子どもの好奇心を尊重し、疑問に対して一緒に調べたり考えたりする時間を持つことが、探求心や知的好奇心を刺激します。また、嬉しい、悲しい、悔しいといった感情を否定せず、なぜそう感じるのかを一緒に考え、言葉にする機会を持つことで、自己認識や感情のコントロール能力が育まれます。
読書や遊びの時間を大切にする
物語を通じて登場人物の気持ちを想像することは共感性を育みます。また、ルールのある遊びや自由な発想で遊ぶことは、協調性、創造性、問題解決能力などを総合的に育む貴重な時間です。特に、子どもが主体的に没頭できる「遊び」の時間は、非認知能力を育む上で非常に重要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は、お子さんの未来の可能性を豊かにする「非認知能力」について、その重要性やご家庭での育み方を紹介しました。
知識やスキルといった「認知能力」とともに、目標に向かって頑張る力、人とうまく関わる力、失敗から立ち直る力、新しいことを思いつく力といった「非認知能力」は、予測困難なこれからの社会でお子さまが自分らしく輝くために、ますます重要になっています。
この力は特別な活動だけでなく、日々の生活の中での温かい関わりや声かけを通して育まれます。ご家庭でのお子さまとの時間を大切にし、その成長を信じて見守ることが、お子さんが自らの力で未来を切り開いていくための大きな支えとなるでしょう。
家庭教師のあすなろでも、お子さま一人ひとりの学習と成長のサポートを行っています。学力向上はもちろん、お子さんが持つ可能性を最大限に引き出すお手伝いをいたします。お子さんのやる気アップや勉強のやり方を伝える無料体験授業も行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!